
Amnaj Khetsamtip -shutterstock-
<総合職第一号としての入社から仕事が私のすべてだったのに...結婚も子どもも役職も手に入れた「女性活躍世代」からパワハラで訴えられた>
1980年代後半に入社した、均等法第一世代の大卒女性たちが、定年を迎え始めている。
彼女たちは、どのようなセカンドライフを迎えているのか。近畿大学教授の奥田祥子さんは「女性総合職第一号として入社して順調に昇進、部長を務めたある女性は、望んでいた『女性初の本部長や執行役員』にはなれず、57歳で役職定年を機に退職した」という──。
※本稿は、奥田祥子『等身大の定年後 お金・働き方・生きがい』(光文社新書)の一部を再編集したものです。
「仕事が私のすべてだったのに...」
「こんな、はずじゃ、なかった! これまで、必死に、仕事に打ち込んできた、んです。私生活だって、犠牲にした。仕事が私のすべて、だった。そ、れ、なのに......。私は、最後の最後で......会社に見捨てられたん、です......」
2020年。なぜ、会社を辞めたのか──。という問いに数分間、押し黙った後、メーカーの広報部長職を役職定年になるのと同時に自ら職を辞した横沢佐恵子(よこざわさえこ)さん(仮名、57歳)は、嗚咽し、言葉に詰まりながらも、懸命に思いの丈をぶつけた。
「これまで会社のことを悪く言うのは極力避けてきましたが......私たち女性の総合職第一号は......実際には “広告塔” のように扱われて......能力を発揮するどころか、活躍するための機会さえ十分には与えてもらえなかったんです。そんななかでも、私は耐えに耐えて、頑張って......『男社会』の会社をうまく渡り歩きながら、上司に実力を認めさせて、部長にまで上り詰めたんです。そ、それ、なのに......役定(役職定年)を機に、全く経験のない営業部でデータ管理の仕事を打診されるなんて......。派遣の女性で十分の仕事。もう “お払い箱” と言っているのと同じじゃないですか!」
総合職第一号としての入社からの経緯を話すなかで、いったんは感情の昂りも治まりかけたかに見えたのだが、会社から役職定年後に打診された部署と職務を説明しているうちに憤りが再燃したようで、また言葉につかえ、うなだれた。
それまで長年の継続インタビューで横沢さんは、彼女自身の昇進などキャリアの節目をはじめ、女性社員の家庭と仕事の両立、管理職登用など女性に関する社内制度が整備され、社員の意識も変化するたびに、葛藤や戸惑い、不満などさまざまな心境を語ってくれた。そして、それを己の糧として前を向いて進んでいくのが彼女の強みだった。
にもかかわらず、この日の取材では、本来の彼女なら口にすることがないであろう、「男社会」を「うまく渡り歩いた」といった自分の会社員人生を皮肉るような言葉遣いや、「派遣の女性で十分」といった非正規雇用の女性スタッフを見下すような物言いも気になった。
「均等法第一世代」としていくつもの荒波を乗り越えて能力を開花させた女性の前に、キャリア人生の終盤で立ちはだかったものは何だったのか。これまで20年間に及ぶインタビューを振り返り、その要因に迫りたい。
40歳で「初の女性課長」就任
横沢さんとは2004年、均等法第一世代の総合職女性が管理職への昇進時期を迎え、どのように職場で能力を発揮してキャリアを築いているのかについて、話を聞いたのが始まりだった。入社以来、最も長く在籍して経験を積み、実績を上げてきた広報部で、社内初の女性課長に40歳で昇進してから1年ほどが経過した頃だった。
濃紺のノーカラージャケットにタイトスカートという落ち着いた色、デザインのスーツ姿に、襟元に白地に淡いピンクの花柄のスカーフを巻いて控え目に可憐さを醸し出す。明瞭ながら少しゆっくりとした口調で、微笑みを絶やさない。肩に力の入らない穏やかな雰囲気だったのが、とても印象に残っている。
「社内だけでなく、社会からも、もてはやされて......均等法(男女雇用機会均等法)が施行された年に、女性総合職第一号として入社しましたが、入社数年で多くが辞めていきました。同期入社したほかの女性2人も、入社2、3年目で早々と退職して、いずれも20代半ばで結婚しました。均等法前の女性たちと何ら変わらない人生を歩んだわけです。せっかくチャンスが巡ってきたのに、残念でなりませんでした。後に続く後輩女性たちの見本にならないといけなかったのに......。奥田さんもそんな苦い経験をされたんじゃないんですか?」
「私は年齢的には均等法第一世代ですが、大学卒業後、非正規で働いてお金を貯めてから海外の大学院に進学したので、入社時期は就職氷河期で、均等法世代とはズレているんです。ただ、同世代としての思い入れは強く、取材を通して皆さんの思いに少しでも近づきたいと努めてきました」
「これからが本当の腕の見せ所」
「そうでしたか。では、説明しますね。単刀直入に言うと......総合職女性たちの気合が足りなかったのだと思いますよ」
「えっ? 気合というと......」
「時代が変わろうとしているのに、その波に乗れなかった人があまりに多かった。男性と肩を並べて仕事をするんですから、厳しくて当然ですよね。でも、それに耐えられなくて......結局は、結婚に逃げたんじゃないでしょうか」
柔和な表情は変わらないが、言葉は至って厳しい。均等法第一世代の女性の多くが入社数年で辞職した理由を会社のせいにするのではなく、本人に突き付けていたのも新鮮だった。
「社内で女性初の課長になって、今後、仕事とどう向き合っていきたいと考えていますか?」
「これからが、本当の腕の見せ所だと思っています。もともと均等法第一世代の私が初の女性課長になるのは決まっていたことですから。だから、仕事ひと筋で頑張ります。自信はありますよ」
これまでもこれからも「仕事ひと筋」
「あのー、失礼ですが......」
「あっ、結婚ですか? お気遣い無用です。結婚も出産もやめて、仕事ひと筋、ってことです。子育てをしていたら、男性と同じように会社の業務命令に従うことができず、課長にはなれていなかったでしょうし、家庭と両立しながら能力を発揮するのは難しいですから」
当時は今とは異なり、女性の管理職登用どころか、女性が出産後も就業継続することが容易ではなかった時代。企業は、女性社員の子育てなど家庭との両立支援策に頭を痛めていたのが実情だった。そんな時代を「仕事ひと筋」でこれからも頑張るという横沢さんが、逞しくも見えた。
過剰な「配慮」への不満
その後、時流に乗って、企業の多くが女性社員の仕事と家庭の両立支援本格化へと舵を切る。横沢さんのように「仕事ひと筋」で頑張ってきた生き方とは異なる女性のライフスタイルを、社会も推奨し、応援するようになっていくのだ。
2007年に政府と経済界、労働界、地方公共団体の合意で「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」が策定されたことを契機に、「ワーク・ライフ・バランス*1」という言葉・概念が広まり始めたことも背景にはあった。
一方で、独身を貫き、男性社員と同様、長時間労働もこなし、地方支社への転勤も経験してきた横沢さんにとっては、子育てをしながら就業継続し、育児休業(育休)だけでなく、時短勤務や時間外労働(残業)の免除、転勤の見合わせなど、さまざまな「配慮」を受けている女性社員の働き方には、物申したいところがあるようだった。
07年頃を境に不満は次第に強まり、笑みを見せることもほとんどなくなる。関西の支社への3年間の転勤を経て東京本社に戻り、広報部の部次長に昇進してから3カ月ほど経った10年のインタビューで、当時47歳の横沢さんは、どうにもやりきれない思いを打ち明けた。
「結婚、出産しても仕事を辞めず、子育てしながら働き続ける女性を増やすことが、世の中の流れだということはわかっています。『女性の社会進出』と言われれば、反論することはできませんし......。でも、どこか、違う、と思うんです」
*1 2008年に労働契約法の条文に「仕事と生活の調和にも配慮しつつ」労働契約を結ぶ、という文言が盛り込まれたことも、ワーク・ライフ・バランスという言葉・概念が社会に浸透するきっかけとなった。
「女の闘いなのかも」
「何が、違う、とお考えですか?」
「育児との両立のために女性社員に過剰に『配慮』することですね。例えば、育休を取得した女性社員のいる部署は欠員1のまま職務を遂行して、職場復帰しても、時短勤務、残業免除などとなると、その分、他の社員の負担が大きくなります。本人も『配慮』、つまり仕事の量も質もセーブしたぬるま湯状態から抜け出すことができず、総合職でも出世の道を逃してしまう。本人が昇進を望まないことも多いですが......。その一方で、負担が重くのしかかったある30代独身の女性の部下が辞めていきました。彼女のつらさに気づいて、十分にフォローすることができずに責任を感じているんです。うーん、何と言ったらいいのか......」
横沢さんが言いよどみ、しばし沈黙が訪れる。自身の考えをうまく言語化しようともがいているようにも思えた。と、急に靄(もや)が晴れたように、誰に語りかけるともなく、ぽつりとこう、つぶやいた。
「女の闘い、なのかも......」
この女性同士の「闘い」が、やがてわが身にふりかかろうとは、この時は予想だにしていなかったことだろう。
女性活躍推進法で加速した女性登用
それからも社会が求める女性社員の働き方、生き方は、ますます横沢さんが歩んできた仕事を第一優先とする道とは異なる方向に向かっていく。育児と両立させながら仕事で能力を発揮し、さらに管理職という指導的地位に就いて活躍していくというライフスタイルである。
第二次安倍内閣が2013年に発表した成長戦略のひとつに「女性が輝く日本」が掲げられた頃から、大企業を中心に女性登用を意識した取り組みが本格化する。その後、女性管理職比率の数値目標などを盛り込んだ行動計画の策定、公表を雇用主に義務づけた女性活躍推進法*2 の施行によって、企業の女性登用推進が一気に加速する。
横沢さんが育児をしながら管理職を目指す後進の女性たちへの嫌悪感や批判を赤裸々に語るようになったのは、女性活躍推進法が全面施行された16年頃からだった。14年に51歳で社内初の女性部長に昇進して采配を振るう一方で、悩みはなおいっそう深まっていたのだ。
「『女性活躍』という国が掲げる崇高な理念はわかりますよ。でもね、職場を混乱させてまで、無理して、育児との両立だけで大変な女性社員を、管理職にまで引き上げて優遇するのはどうかと思うんです!」
それまでも多少の憤りを露わにすることはあったが、16年のこの時のインタビューでは声を震わせて怒りをぶちまけたのが鮮烈に脳裏に焼きついている。
*2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律。10年間の時限立法。16年から女性管理職比率の数値目標などを盛り込んだ行動計画の策定・公表が、常時雇用する労働者301人以上の大企業に義務づけられた。19年の改正法施行により22年から義務づけの対象が、同101人以上300人以下の中小企業にも広がった。同100人以下の事業主は努力義務。
“数合わせ” の女性優遇は許せない
「混乱、とは職場でどのようなことが起こっているのですか?」
「まず、リーダーとしての能力が備わっていないのに、女性管理職の数値目標を達成するため、つまり “数合わせ” の不適切な女性優遇措置で課長に昇進したために部下を管理・監督できないことです。うちの部でも人事部から打診を受けた時、きっぱりと断ったんです。でも、『社の方針だから頼む』と言われて......。対外的なPRも狙っているのでしょうが、女性の中でも敢えて子育て中の者を優先して登用しようとしているようで......納得いきません。下駄を履かせて課長に就かせてもらったにもかかわらず、子どもを保育園に迎えに行くとかで平気で残業せずに退社するし......。おのずと人間関係はギスギスするし、職場全体のパフォーマンスが低下しています。許せない! すべて部長の私の責任になるんですから......」
横沢さんの会社の女性登用が本当に不適切だったのかどうかは、わからない。ただ、幼児を育児中の女性課長の誕生が、部内に多少なりとも混乱を招いたことは確かだろう。
その後も取材するたびに、部下の女性課長だけでなく、全社的に少しずつ増えている女性管理職への批判の声がますます強くなっていった。
辞職の背後に女性部下への「パワハラ」
そうして、冒頭の2020年のインタビューで、むせび泣きながら気持ちを激しくぶつけたシーンへとつながるのだ。役職延長を2度重ねて57歳まで部長を務めた横沢さんにとって、次の職務として打診された未経験の営業部でのデータ管理は、「これまで必死に頑張ってきた自分のキャリア人生を否定されたようだった」と、感情の昂りが治まってから彼女は静かにつぶやいた。
その後、定期的に連絡をしても返信がない状態が続き、ようやく取材が実現したのは、22年のこと。退職後1年半は預貯金を取り崩して暮らしていたが、しばらく前から大学時代の友人の紹介でウェブライターの仕事を始めたのだという。
「広報部時代の経験を生かして、ライターを細々とやっています。会社員時代に比べると、誰がどう評価してくれるのかもわからない戸惑いもありますが......また社会とつながれて少しは気持ちが上向いたような気がしています」
そして、思わぬ告白を聞くことになる。広報部の部長時代、「女王蜂症候群*3」とも呼ばれる、女性上司による女性部下へのパワーハラスメント(パワハラ)の加害者として訴えられたというのだ。
「ずっとお話ししたいと思っていて、できていなかったのですが......。実は、仕事を辞める1年ほど前に女性部下からパワハラで訴えられていたんです。当時は事実無根と突っぱねましたが......パワハラに該当する部分はあったんでしょうね。残業や転勤もせずに子育てと両立させながら課長になり、有能な彼女が腹立たしかった。嫉妬していたのかもしれない。今ならそう、思えます......」
*3 女性が女性部下を敵と見なして手厳しく対応する現象。男性優位社会で努力して指導的地位を獲得した女性ほど、自分より職場で下位の有能な女性を自身の地位を脅かす存在と見なすという。女王蜂がライバルとなるメスと敵対する習性から名づけられた。米国・ミシガン大学の心理学者3人が発表した論文で初めて登場した概念で、1970年代に欧米で話題になった。
時代の変化に追いつけなかった
1カ月に及ぶ関係者のヒヤリングでパワハラ認定はなされなかったが、周囲から白い目で見られ、「女性部長は感情的になる」「女性部下とは仲が悪い」と陰口をたたかれているであろうことは想像に易かった。
「女性部下からのパワハラの訴えがあったために、私が部長の先に望んでいた、いずれも女性初となる本部長や執行役員に就く道はなくなったのだと考えています。男が決めたルールに従って働いているうちに、当初は不本意だった『男社会』に違和感も抱かなくなっていました。管理職として順当に出世させてもらい、感謝しています。でも......仕事も家庭も手に入れて、さらに出世までする『女性活躍』社会へと、日々刻々と変わっていく時代の変化に、男では珍しくない仕事ひと筋できた私自身が追いつけなかったのでしょうね。それで自分を見失い、燃え尽きてしまった。もう少し早く、意識を変えられていればとも思いますよ」
自身を俯瞰して見ているようだったのは、冷静さを取り戻した証(あかし)であるようにも思えた。
24年の新春、複数の編集プロダクションと業務委託契約を結んでフリーランスでウェブライターを続けている横沢さんに改めて話を聞いた。
「今年度、私の同級生たちは定年退職を迎えました。管理職を経験して定年まで同じ会社で働き続けた女性は、ゼミで私だけですけれど......。同級生の男性たちが試行錯誤しながらも頑張っている姿を見聞きして、私もためらっていてはダメだと思い直しました。1年ほど前からスキルアップにも取り組んで、ライターの仕事に本腰を入れるようになったんです。誰かが必要としてくれるうちは、まだまだ、続けますよ。う、ふっ......」
20年に及ぶ継続インタビューで、横沢さんがリラックスして自然な笑みを浮かべたのを見たのは、出会った頃以来だった。
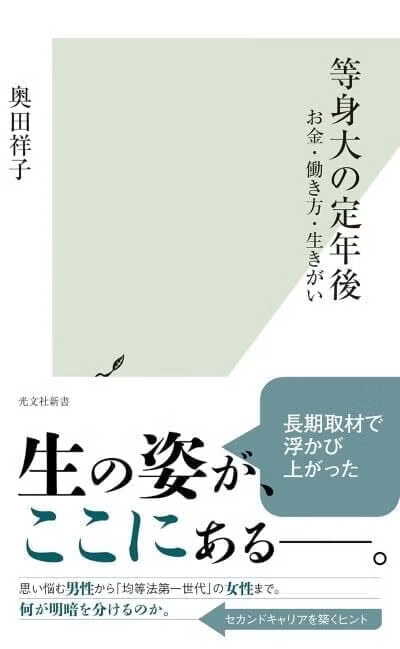 奥田祥子『等身大の定年後 お金・働き方・生きがい』(光文社新書)(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)
奥田祥子『等身大の定年後 お金・働き方・生きがい』(光文社新書)(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。





